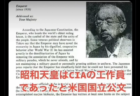30回を数えた「司法が認めた沖縄戦の実態」。その内容を執筆者の文箭祥人が振り返った。取り上げた証言の中から見えたのは「壕追い出し」の実態だった。追い出されたのは住民だった。では、誰が追い出したのか?それは日本兵だった。(取材/写真 文箭祥人)
6月23日、沖縄は「慰霊の日」を迎える。沖縄県南部の糸満市摩文仁にある平和祈念公園で追悼式が行われる。公園内に「平和の礎」が置かれている。そこには、国籍を問うことなく、軍人・民間人の区別なく、沖縄戦で亡くなった24万を超える人々の名前が刻銘されている。この連載で取り上げた陳述書に書かれている死没した人たちの名前も刻まれている。
さて、この連載は今回で節目の第30回。これまで、原告28人の陳述書を取り上げてきた。日本兵の「壕追い出し」によって、住民は弾が飛び交う戦場に放り出され、亡くなった、負傷した、という沖縄戦の実態を多くの原告が証言した。「壕追い出し」の証言は連載第3回の内間善孝さんの証言に始まる。
内間善孝さん
「壕に数人の日本兵がやって来ました。日本兵は母に向かって、「4人も子どもがいて、敵に見つかったらどうする。壕を出ていけ」と言いました。日本兵に逆らえず、壕を出ました」
内間さん家族6人は、壕を追い出され戦場を逃げまどう。母と2歳の三男は米兵に撃たれ死亡し、4歳の次男は生き延びたが栄養失調で亡くなった。戦後、内間さんは戦場で見たものや死体・火薬のにおいが蘇り、強度の不眠が続く。戦争PTSDと診断された。内間さんはこう陳述書に書いている。
「日本兵が私たちを安全な壕から追いやり、危険な戦場のただ中に放り出しました。家族を死なせたのは国です」
内間さんの証言に続いて、第4回の比嘉千代子さん。
「壕に日本兵が来て、「この壕は兵隊が使うから民間人は出るように」と言われました。一人の男性が「この壕は私たちの壕だ」と言うと、「きさまらの首は1銭5厘だ。ここから出るように」と命令しました。他の住民たちとともに壕を追い出されました。日本兵は悪魔だと思いました」
米兵の手榴弾や銃撃により比嘉さんの父と親戚3人が死亡。比嘉さんは砲弾の破片によりけがを負い、身体の中に砲弾の破片が残っている。さらに、花火の音が弾がバンバンするように聞こえ、火薬の臭いが蘇る。戦争PTSDと診断された。
「日本軍の兵隊に壕から追い出されなければ、みんな生きていたはずです」
山城照子さん(第5回)。
「鈴木軍曹と名乗る兵士が部下3人を引き連れてやってきました。「この壕は私たちが使うから出ていくように」と強い口調で命令しました。母は「壕を出たら生きていけない。半分ずつ使いましょう」と話したところ、鈴木軍曹は渋々、承知しました。日本兵は安全な奥の方で、私たちは危険な壕の入口付近でした」
當眞嗣文さん(第12回)。
「母と私たちきょうだいは墓に隠れていました。日本軍が来て、出ていくように命令されました。母を先頭に私たちは墓から出されました。その際、砲弾が近くに落ち、弾の破片が母の顔面を直撃し、母は即死しました」
當眞さんらは南部へ避難し、壕に隠れていた。そこへ日本兵が現れる。
「日本兵に壕の明け渡しを強制されました。他の壕に移る時、艦砲弾が近くで爆発、その破片が飛んできて、姉が背負っていた妹の横腹を貫通しました。その日のうちに妹は亡くなりました」
沢岻孝助さん(第13回)。
「私の家に日本兵がやって来て、私たち家族は家を追い出されました。両親と4人の妹とともに近くの墓に避難しました」
墓での避難生活が始まって3か月後。
「日本兵がやって来ました。すぐに墓を出るようにと私たちに言いました。日本兵の説明はアメリカ軍がやってくるということでした。父が「どうせ死ぬなら墓の方がよい」と言いました。すると、日本兵は「捕虜になったらスパイになるから、墓を出ないのなら子どももみんな殺す」と言って、日本刀を抜きました。それを見て父は墓を出ることを決めました」
沢岻さん家族は南部へ移動。馬小屋を見つけ、そこに避難することになる。
「雨のように砲弾が飛んできて、馬小屋にも直撃しました」
両親と兄が死亡。沢岻さんは頭と足にけがを負う。戦後、脊髄に弾の破片が入っていることがわかった。身体のしびれに苦しむが、それは戦争PTSDによるものだと診断された。
山岡芳子さん(第15回)。
「日本軍が現れ、「ここは軍が使う。住民は南部へ出ていけ」と命令され、やむなく壕を出ました」
山岡さん家族は南部へ行き、壕を見つけ、そこに避難する。
「兵隊から壕を出ていくように命令されました。私たちは爆弾が飛び交う中を逃げに逃げました」
移動中に弾に襲われ、母と兄、妹が死亡。山岡さんは右頬と額、目をやられ、目がよく見えなくなり、やけども負う。一緒に移動せず、軍の手伝いをさせられていた祖父と父は艦砲射撃で即死した。山岡さんは祖父、両親、兄、妹を亡くし、戦争孤児となった。
この裁判は、沖縄戦の民間人被害者が沖縄戦を遂行した国に国家賠償を求めたもの。原告は陳述書を裁判所に提出し、法廷で被害実態を訴えた。「壕追い出し」などの被害実態は認められたが、敗訴に終わった。そもそも、沖縄戦で被害を受けた民間人を補償する法律があれば裁判に訴える必要はなく、法律がないから裁判に訴えたのだ。
なぜ沖縄戦で被害を受けた民間人は、国に補償されないまま放置されるのだろうか。
戦後間もない時代に遡り、戦後処理の経緯を振り返ると、見えてくるものがある。キーとなるのは、戦傷病者戦没者遺族等援護法。
戦後、日本は連合国軍最高司令部(GHQ)の占領下に置かれた。1946年、GHQの指令により、一部を除き軍人恩給が停止された。
恩給は、公務員が公務のために死亡などした場合において、国家に身体、生命を捧げて尽くすべき関係にあった、これらの者及びその遺族に給付される国家補償を基本とする年金制度。旧軍人本人と旧軍人の遺族には軍人恩給が支給される。
なぜ、GHQは軍人恩給を停止したのか。軍人恩給制度が世襲軍人階級の永続を計る一手段であり、世襲軍人階級が日本の侵略政策の大きな源となった、そうした軍人恩給制度は停止しなければならないとした。
1952年4月28日、日本は主権を回復する。その2日後、戦傷病者戦没者遺族等援護法(援護法)が公布され、米軍占領下にあった沖縄は1953年から適用された。援護法制定時における援護法は、軍人・軍属の公務上の死亡、負傷、疾病に関して、国家補償の精神に基づいて援護を実施するというものだった。沖縄戦の民間人被害者や全国の民間の空襲被害者は適用外とされた。ただし、軍人・軍属でなくとも軍の要請に基づく「戦闘参加者」は軍属とみなされた。
沖縄戦は多くの住民を巻き込んだ。住民のなかで、どういう人を「戦闘参加者」とするのかが問題となった。そこで、厚生省は1957年3月からおよそ1か月半にわたって、事務官を沖縄に派遣し、沖縄戦被害の調査を行った。
この調査に関する厚生省の事務官の報告書が残っている。『沖縄県史』に、「この報告書は、日本政府が沖縄戦の実相をどのように把握していたのかが示されており」とした上で、この報告書について次のように書かれている。
「この報告書で、「住民を威嚇強制のうえ壕からの立退きを命じて己の身の安全を図」ったりなどの沖縄住民に対する残虐行為を行っており、「皇軍のなれの果てかと思わせる程の」「蛮行」だと批判している」
続けて、こう記されている。
「その上で、「非戦闘員である住民安住の壕を軍の必要に基いて、強制収用して、壕外に放逐し、無辜の老幼婦女子を死地に投じて多数の犠牲者を生ぜしめて」おり、「かかるケースも当然軍の戦闘に協力したものと見るべき」であると指摘している」
冒頭で紹介した陳述書に書かれている「壕追い出し」の犠牲者は、「軍の協力者」だと厚生省の事務官は把握していた。
この報告書を経て、厚生省はどういう人を「戦闘参加者」とするかを明記した「戦闘参加者概況表」を作成し、「戦闘参加者」は20のケースがあるとした。その一つがこれだ。
「壕の提供」
そして、「戦闘参加者」をどう扱うかを定める「沖縄戦の戦闘参加者の処理要綱」を決定し、1958年に援護法が改定され、「戦闘参加者」は準軍属という身分となり、援護金が支給されるようになった。
厚労省が監修した『援護法Q&A』に「戦闘参加者とは」にこう記述されている。
「沖縄のように日本住民が居住する地域に米軍が上陸して、官民が一体となって戦闘が行われた地域においては、日本軍の戦闘を有利に導くため、軍の要請による弾薬・食料の運搬、炊事、避難壕の提供など戦闘を幇助する軍事行動に参加した者も戦闘参加者として処遇されます」

援護法上、日本軍に協力して「壕の提供」をして沖縄戦を闘った住民が出現した。実際、「壕の提供」をした住民はいるのだろうか。
援護法の適用を受けるにあたって、住民本人あるいは遺族は「申立書」に被害状況などを記入し、各市町村に提出する。市町村、琉球政府が審査を行い、最後に厚生省が審査をし、援護法適用に該当するのかどうかを決める、こういう手続きになっている。
ここでキーなるのが「申立書」だ。書き換えが行われたという。
『沖縄県史』に「申込書」に関して、次のように記述されている。
「沖縄県民から提出された「申立書」に対し、厚生省は「戦闘参加内容が消極的に失する」として「返却」し、「当時の戦況から判断して」、「死亡原因」が「積極的戦闘協力によるもの」ではないかと、琉球政府に記載内容を書き換えるよう指導を行う場合もあった」
さらに、沖縄戦の調査・研究に長年取り組んでいる沖縄国際大学名誉教授石原昌家の著書『国家に捏造される沖縄戦体験』に「申立書」にかかわった琉球政府職員へのインタビュー内容が書かれている。この職員は沖縄戦の遺族に直接面談し、「申立書」作成にかかわった。
「オバァたちのなかには、友軍のみなさんに自分からすすんで「壕を使ってください」と言ったことは一度もない、「出て行け!」と言われたんで出たんであって、「自分から出て行ったのではない!壕を提供したのではない」と、かなり怒って、調査員に楯突いたオバァもずいぶんといましたよ。こんなことでは、申立書の書きようがないし、戦闘参加者にするには厚生省作成のマニュアルに当てはまるようにするにはオバァたちの証言とはまるで反対のことを書かないといけないので、壕の提供になるように書いてあげたんです」
なぜ、ウソの「申立書」を書いたのか。沖縄戦の時、この職員は撃沈された疎開船・対馬丸に乗船する予定だった。しかし、集合時刻に遅れ、別の船に乗り、撃沈されなかったから生き残った。「申立書」を提出する住民も、それを審査する職員も沖縄戦に巻き込まれたのだ。
「なんとしてでもこの遺族のみなさんの生活を助けてあげたい、そんな気持ちがどんどん強くなり、ウソでもいいから、援護金がもらえるようにしようと思いたったんです」
また、次のように話している。
「「申立書」のほとんどは琉球政府援護課担当が書いたものです。本人が直接記載したものはわずかしかありません」
沖縄戦後、住民は苦しい生活を余儀なくされた。援護法の担当職員が厚意によって書き換えを行ったのだ。
「戦闘参加者」は何人いるのか。沖縄県が発行した『沖縄の福祉』(昭和58年版)に「一般戦没者数について 戦闘参加者 55,724人 一般県民 38,276人 計94,000人」と記されている。沖縄県に取材したが、「戦闘参加者」のうち負傷者は何人いるのか明確にならなかった。
書き換えられた「申立書」は歴史認識に影響する。「申立書」を読めば、‘多くの住民は壕を提供するなどして、軍に協力して軍とともに沖縄戦を戦った’と解釈され、こうした歴史認識が引き継がれることになる。「沖縄戦の実態を歪めることにつながる」と危惧する声が研究者から上がっている。その意味で、「壕追い出し」を証言する原告の陳述書を司法が認めたことは歴史的に大きいと言える。
「今時の戦争において国民すべてが何らかの犠牲を被っています。援護法はこのうち、軍人軍属など国と雇用または雇用類似の関係にあった者が戦争により障害を負い、または死亡した場合に、障害者本人や死亡者の遺族に対して補償を行う制度です。一方、空襲によって負傷したり、死亡した一般の戦災者は、国と雇用関係がありませんので援護法による給付は受けられません」
GHQにより停止された軍人恩給はその後どうなったか。軍人恩給は援護法が公布された翌年1953年、復活した。援護法の対象者は軍属・準軍属が中心になり、軍人やその遺族の大半は軍人恩給に移行した。軍人恩給は今も続いている。軍人恩給の戦後累計金額を総務省に取材すると、「昭和28年度(1953年度)から令和6年度(2024年度)までの予算額の積み上げで約53兆円」に上る。
国との雇用関係がない、少なくとも約4万人とされる沖縄戦の一般民間人被害者を対象にした法律を求める動きが1970年代から始まる。
沖縄県が発行した『沖縄の援護の歩みー沖縄戦終結50周年記念』にこう記述されている。
「昭和46年(1971年)に沖縄戦被災者補償期成連盟が結成された。県は同連盟に対し補助金を交付し、沖縄戦で被災した負傷者、死没者の名簿を作成させた。同連盟は同名簿に基づき、一般戦傷病者及び戦没者の遺族に対し援護法に準ずる措置を講じてもらいたい旨の陳情を、昭和48年、49年に行った。県はこれらの要請を受け、昭和48年(1973年)から昭和63年(1988年)までの間に国に継続的に強く要請を続けて来た」
要請先として、総理大臣・厚生大臣・大蔵大臣・総務長官・参議院沖縄問題特別委員会などの名前が並んでいる。
こうした沖縄県の要請に対して、国はどう対処したのか。『沖縄の援護の歩み』に続けてこう記載されている。
「しかしながら、国においては、戦後残された問題を検討するため昭和57年(1982年)6月に政府は、総務庁長官の私的諮問機関として「戦後処理問題懇談会」を設け、恩給欠格者問題、戦後強制抑留者問題、在外財産問題等のいわゆる戦後処理問題について検討することとした。政府としては同懇談会の趣旨に沿って所要の措置を講じることを基本方針とした」
沖縄戦で死傷した一般民間人問題は「戦後処理問題」として検討されなかったことになる。
1972年に全国戦災傷害者連絡会(略称:全傷連)が結成され、民間の戦争被害者に対する援護法の立法化を国に要請する運動を始め、沖縄からも声が上がった。運動は2013年まで続き、この間、野党が法案を14回提出したが、実現しなかった。
1975年、日本弁護士連合会(日弁連)は「民間戦災者に対する援護法制定に関する決議」を採択した。軍人・軍属・準軍属に限定された援護法は法の下の平等に反し、アジア・太平洋戦争の体験の上につくられた平和憲法の基本精神にも背くものだとして、民間戦災死者、傷害者に対する援護法をすみやかに制定すべきだと決議した。
2015年、沖縄県議会は国に対して、「民間戦争被害者を救済する「新たな援護法」の制定を求める意見書」を提出した。「援護法により援護された被害者以外の数多くの未補償の被害者(死没者の場合はその遺族)に対して国の責任において援護措置を決定し、相当の援護金等を支給する「新たな援護法」を制定することを強く要請する」という内容の意見書だ。
2010年に全国空襲被害者連絡協議会(略称:全国空襲連)が結成され、全傷連の運動は引き継がれた。2021年、全国空襲連と連帯する自民党を含めた超党派の国会議員連盟が民間の戦争被害者の救済問題を解決しようと空襲被害者等救済法案をまとめた。法案には沖縄戦被害者が含まれる。
このように沖縄戦で死傷した一般民間人を対象にした法律を求める声が、市民社会から上がり、沖縄県や沖縄県議会が国に立法化を要請した。
沖縄戦の民間人被害者が起こした裁判の弁護団長だった瑞慶山茂弁護士はこう述べている。
「沖縄戦住民被害に対する立法化を進めて行きたい。それには、裁判所が認めた住民被害・戦争PTSDの事実が重要になります。立法化の根拠になるからです」
司法が原告の被害実態を認めた事実が法律を制定する場合の基礎となるという。
裁判に訴えた原告ら被害者は敗訴後、新規立法による救済を訴え、活動してきた。沖縄戦や南洋戦の民間人被害者への戦後補償を求める「民間戦争被害の補償を実現する沖縄県民の会」が結成され、全国空襲連と共同して立法化運動を行っている。