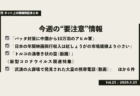なぜ、大阪から沖縄へ行くのか
「沖縄戦での被害者の傷は癒されることなく続いている」
それは小冊子に書かれていた。2009年だったと思う。私は大阪の放送局で記者をしていて、太平洋戦争中に起きた大阪空襲の被害者を取材していた。それは太平洋戦争中の被害者について書かれた小冊子に記されていた。
その時は私自身、沖縄戦をめぐる訴訟を取材することになるとは思ってもいなかったが、その言葉は心のどこかにひっかかっていた。
それからしばらくして私は記者の仕事を外れた。本意ではなかったが、会社の人事の都合と割り切って、辞令通りの業務に着いた。
それでも、大阪空襲訴訟には関わり続けた。それは取材者というより、原告を支援する側といった役回りとなったが、自分の中ではそうした立場はどちらでも良かった。
戦後補償。日本が中国や韓国など国外から常に突き付けられてきた問題。しかし、それは国内でも突き付けられてきたことをどれだけの人が認識しているだろうか?
戦後補償がなされた日本人はいる。軍人軍属だった人だ。そういう人たちには手厚い援護がある。しかし、空襲の被害を受けた一般の人には何らの補償もされていない。
私が大阪空襲訴訟に関わり続ける理由はそこにある。泣き寝入りさせられる人々、その現状にまったく納得できないから、戦後補償問題にかかわり続け、それが沖縄に続いている。
ここで簡単に、2008年提訴の大阪空襲訴訟について触れておきたい。大阪空襲でけがをして障がい者となった被害者や孤児となった被害者が、国を相手に謝罪と補償を求めた裁判だ。生後2時間の時、焼夷弾が落ち、片足を奪われた女性や家族が焼夷弾で亡くなり孤児となった女性、指が自由に動かなくなり、顔がケロイドとなった男性…。
爆弾の破片が飛んできて左足を失った女性、当時6歳。「私の足はトカゲのしっぽみたいにまた生えてくる」と信じていた。「どうして戦争を止められなかったの?」と母親に聞くと「知らないうちに始まっていた」
こうした空襲被害の訴訟は、2007年、東京大空襲の被害者も国を相手に裁判を起こしている。そして東京大空襲訴訟は2013年、大阪空襲訴訟は2014年、いずれも最高裁で敗訴が確定している。空襲被害者の訴えは退けられた。裁判で負けた後も、原告だった人々は立法運動に取り組んでいる。
そして沖縄戦だ。東京大空襲訴訟の弁護団にいた沖縄出身の瑞慶山茂弁護士らが中心に、訴訟の準備が進められた。
沖縄は日本で唯一、太平洋戦争で地上戦を経験した。これは沖縄の誰もが知っているが、実際にそれで国を訴えるという動きは簡単ではなかった・・・とは後に瑞慶山弁護士から聞いた。
「沖縄戦による身体障がい者が多く、精神異常、耳が聞こえない、目が見えない、字が書けないと大変な状態だった。ほとんどが生活保護を受け、収入も少なく貧しい生活を送っていた」
それでも徐々に準備を進め、2012年に提訴。沖縄戦の民間人の被害者も東京、大阪に続いて国を相手に謝罪と補償を求めた。
その沖縄戦の裁判が始まったことは耳にしていたが、大阪に暮らす私はほとんど情報を得ることができず、報道もほとんどなかった。大阪や東京の空襲訴訟の関係者に聞いてもわからなかった。
瑞慶山弁護士に連絡をとり、その内容を取材し始めた。そこで、ある事実に気づかされた。沖縄戦の被害者は空襲被害者とは異なる側面を持っているという事実だ。それは、被害者の多くが、日本兵の加害によって亡くなったり、負傷した人たちだということだ。空襲による被害は米軍の爆撃によるもので、日米両軍の地上戦に巻き込まれた沖縄戦の被害とは全く異なる。日本兵とは日本政府の軍人だ。その軍人が加害者ということは、つまり日本政府が直接の加害者ということだ。
「大変なことではないか・・・」
そう思った私は直ぐに沖縄に行くことにした。ただ、残念ながらそう簡単に沖縄にはいけない。会社の業務の調整をしなければならず、最初に行けたのは、2015年9月30日、那覇地方裁判所での結審の日だった。
9月末だというのに、その日の日差しの強さを覚えている。かりゆし姿の男性や南国色の服を着た女性が、日差しを避け、木の陰に立っていた。原告はみな高齢だ。杖をついている人、背中が丸くなり歩幅が狭くゆっくりと歩く人。20人ほどが、沖縄の各地から那覇市樋川の裁判所前に集まった。
「1100ページになる最終準備書面を裁判所に提出しました。一方、被告・国はわずか7ページ、ひどい話だ。強く裁判所に迫っていきます」
原告に向けて説明する瑞慶山弁護士の姿があった。
当然、沖縄の地元メディアの記者が取材をしている。地元テレビ局やNHK沖縄放送局のテレビカメラがまわっていた。地元紙は大きく裁判を取り上げている。
「NHKも取材しているのかぁ・・・」
私には意外だったのは、NHKは全国組織だからだ。NHKや全国紙の記者も取材しているのに、なぜ本土でニュースにならないのか?沖縄では大きなニュースになっているという現実。それが本土では伝わらない現実を目の当たりにした。
その時、瑞慶山弁護士から、「大阪から来たんだから、何か言ってくれませんか?」と声をかけられた。これは本土から来た私の義務だと感じた。沖縄を孤立させてはいけない。否、けして沖縄は孤立してはいない。気が付くと、私は「大阪から来ました」とマイクに向かって叫んでいた。
そして法廷。裁判官は合議制で裁判長を中心に3人が鎮座している。きょうで審理を終えることになる。
原告にとって最後の陳述の機会だ。原告の一人が陳述書を読み上げた。高齢にもかかわらず、しっかりとした口調だった。裁判官にはどう聞こえているのか?そう思いながら目の前で語られる被害に聞き入った。
そして裁判を終わった。大阪から来たのは私一人だった。その日、瑞慶山弁護士らに話を聞いた。
瑞慶山弁護士の言葉

この裁判のきっかけは、瑞慶山弁護士だったとは既に書いた。当時、千葉県が拠点の瑞慶山弁護士は、東京大空襲の訴訟に関わる中、沖縄戦被害についても調査を深めずにはいられなくなったという。
「沖縄県内で国に対する法的責任の追及が全く行われていないことに驚愕した」
瑞慶山弁護士は沖縄に戻り、電話で法律相談を始めた。
「きめ細かく、当時の経験を話してほしい」
そういう思いだったという。その結果、被害者の声が集まる。そして2012年8月15日、提訴となった。
瑞慶山弁護士は私に言った。
「沖縄戦の悲しい物語を聞いて、それで終わりにしてはならない」
衝撃だった。
確かに、この日の原告の陳述を聞くと、その惨状に圧倒され、悲しさでいっぱいになってしまう。なぜ、被害を受けたのか、なぜ戦後、国から何らの謝罪も補償もないのだろうか、こうした疑問を持つまでには至らない。瑞慶山弁護士は聞く側に思考することを求める。
瑞慶山弁護士は更に言った。
「沖縄戦被害は過去のことではない」
私はその言葉の意味をわかった・・・と、その時は思っていた。しかし、本当にわかったのか、自問が始まる。この裁判を追う中で、この言葉の意味をつかもうとした。「沖縄を孤立させない」との思いでマイクを握ったその日以降、法廷が開かれるたびに大阪から沖縄に行った。それは沖縄を「孤立させない」という思いからだったが、私は沖縄で裁判を通じてその瑞慶山弁護士の言葉の意味を考えることとなる。私がこの連載を書くことを決めたのは、この瑞慶山弁護士の言葉の意味を多くの人と考えたいためだ。
連載2回目の今回、私のことを書かせて頂いた。次回からが本番だ。「司法が認めた沖縄戦の実態」。更に、詳しくみていきたいと思う。(続く)