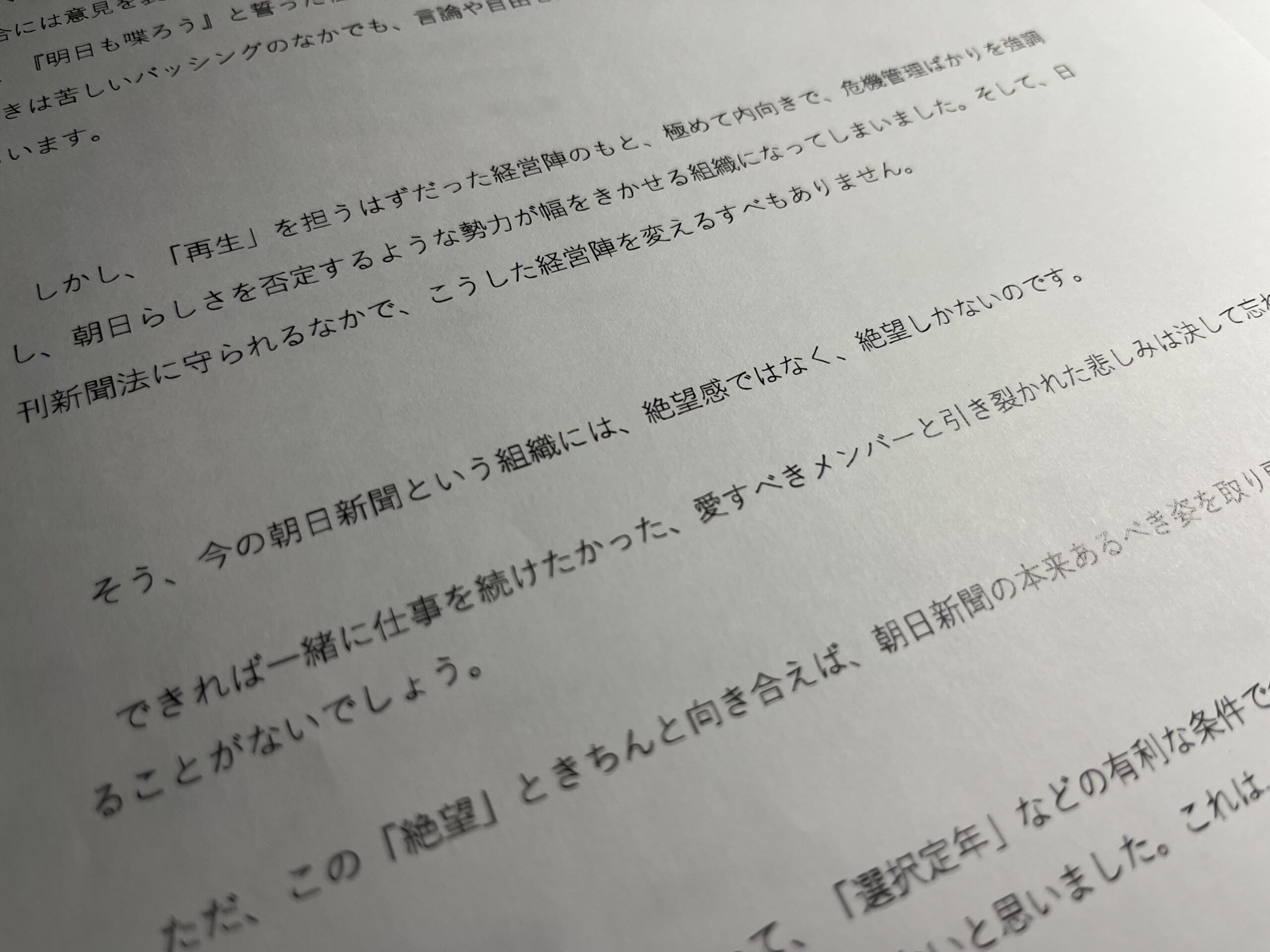
「本日、朝日新聞を退職することになりました」。
冒頭にこう書かれた「退職挨拶文」。これは南彰さんが記者として過ごした朝日新聞社にあてた挨拶文だ。週刊文春が報じたことで広く知られ、メディア関係者の間で話題になっている。
朝日新聞を辞めた南さんが選んだのは沖縄の地方紙である琉球新報社での記者生活。既に沖縄での記者生活を始めたことを南さんは自身のSNSで報告している。
一般的に地方紙から全国紙、全国紙の中でも他の新聞社から朝日新聞社を目指すのが慣行となっている。こうした中で、南さんの今回の決断は極めて異例だ。
一方で、南さんの動きは、新聞ヒエラルキーのトップに立つ朝日新聞と言えども安泰でいられなくなっている昨今のメディアの状況を先取りした動きなのかもしれない。この南さんの動きが一つの契機となり、ある種の地殻変動が起きるかもしれない。
この「退職挨拶文」はメディア史に記録されるべき第一級の資料だ。そう考えたInFactは南さんの挨拶文を入手。ここに全文を公開する。
これは単なる興味本位で掲載するものではない。この記者の考えを共有することで、これからの新聞及びメディア全体の在り方を考えるための極めて重要な視座を得ることができる。そう考えての掲載だ。是非、その思いで「退職挨拶文」を読んで頂きたい。(立岩陽一郎)
朝日新聞に出した「退職挨拶文」
本日、朝日新聞を退職することになりました。
初任地の仙台に着任したころは、先輩から「どこかぼんやりとした印象のある、ひどく頼りのない青年」と評されていました。あれから21年半。編集局はもちろんのこと、関連会社も含めた多くの部署の皆さんに支えられて、常に居場所と出番に恵まれてきました。本日付の素敵な「卒業新聞」までつくっていただきましたが、今日の自分があるのは読者を含めた朝日新聞のおかげでしょう。お世話になった方々には感謝の気持ちでいっぱいです。
退職届を出して以降、多くの方から「なぜ」と尋ねられてきました。文春をはじめ、さまざまなインタビューの要請がありましたが、なかなか応じる気持ちにはなれませんでした。まずは社内に残る皆さんに、朝日新聞という社会的資産をどう生かし、次世代に引き継いでいくのか。それをじっくり考えてほしいと思ったからです。
◇ ◇
「長期的にみると、全国紙で残るのは日経と一般紙1紙」
ノンフィクション作家の下山進さんに言われたのは4年前。『2050年のメディア』の出版直後に招いた新聞労連の役員会です。
「1紙の一般紙は」と尋ねた答えは予想通り。動乱期のメディアの攻防を描いた著作でも、読売の山口寿一社長が主役で、朝日は主要プレイヤーと位置づけられていなかったからです。意見が異なる部分もありましたが、その見通しは現実味を帯びています。
ABC協会の調査では、読売の朝刊発行部数は、朝日、毎日、産経の3紙の合計を上回り、日経を含めた全国紙5紙のシェアで45%。各社で実売部数にばらつきがあるとはいえ、読売のシェアは突出しています。地方取材網を維持し、購読料も据え置いている山口社長は「他紙が新聞の公器としての使命、読者・国民の利益をどこまで熟慮したかは不明」と皮肉りながら、「価格据え置きを生かして、全国紙におけるシェアをさらに高める」とグループ内に発破をかけています。
読売が「唯一無二の全国紙」を掲げ、シェアにこだわるのは、メディア業界の再編を見据えているからです。業界トップであれば「再編される側」ではなく「再編する側」として、次の時代の主導権を握れると考えています。
「世界最大の発行部数を有する読売新聞と利用者数国内最大級のLINEヤフーが共同して発信することで実効性を高める。他メディア等にもプライバシー重視を呼びかける」
10月5日に読売とLINEヤフーが出したインターネット空間の健全性に関する共同声明もそうした姿勢がにじんだものでした。さらに、フェイクニュースや広告詐欺などの氾濫を抑止するデジタル技術の「オリジネーター・プロファイル(OP)」も電通と一緒に推進しています。
読売は2013年から2年連続の4期8年、新聞協会長を務めていました。異例の長さとなった間に、軽減税率の適用や、外資による輪転機メーカーの敵対的買収阻止などを主導し、業界を掌握しつつあります。そして、渡邉恒雄・グループ本社代表取締役主筆の退任後には、一気にデジタルも本格展開する準備を進めているわけです。
◇ ◇
私が新聞労連の委員長の打診をされたのは、そうした業界の変動が進行していた2018年。39歳のときでした。
安倍長期政権のもとで民主主義のルールが変質し、メディアの分断が進行。また、社内でもリベラルな言論を封印しようとする雰囲気が広がり始めた時期でした。
「朝日新聞が壊れそうなんだから、それどころじゃないだろ」
信頼する社内のメンバーからは相当引き留められました。打診の際の言葉も「労連委員長は朝日で出世しないけどよろしく」という包み隠しのない言葉でした。
それでも、メディア業界の曲がり角でさまざまな問題が噴出しているなか、誰かが引き受けないといけない。いまある自分たちのやり方やポジションをただ守ろうとするのではなく、次世代にいかにより良いメディア環境を引き渡していくかを起点に考え、そのなかで持続可能性のあるニュースの生態系をつくっていくことが必要ではないか。そうした公共性を追求するなかから、朝日新聞の今後に役立つ部分もあるのではないか。そう考えて引き受けることにしました。
合言葉は「ネクストジェネレーション」。任期2年の労連での活動の根底にあったのは、デジタル社会への対応でしたが、これは単に紙がデジタルに置き換わるという話ではありません。マスメディアが情報の出口を押さえていた「垂直型」の関係性が崩れ、市民社会との関係が「水平型」になったからです。取材の手法なども可視化されるなかでいかに市民社会から信頼され、仲間と感じてもらえる存在になれるのか。「権力とメディア」「市民社会とメディア」の関係性の見直しと、私たちの役割を明確にすることが肝でした。
この変化は、大阪勤務だった2013~15年に、SNSを駆使する橋下徹・大阪市長らと記者会見などで対峙するなかで体感していました。安倍政権下で起きた首相官邸の記者会見問題を重視したのも、見直しの主戦場の一つだと考えたためです。
そして、報道での主張と一致した組織風土、体質への変革も不可避でした。
厳しく突きつけられたのが、2020年5月に発覚した黒川弘務・東京高検検事長(当時)と朝日・産経社員との「賭け麻雀」です。
旧知の当事者の顔を浮かべると心が痛みましたが、「『賭け麻雀』は市民や時代の要請に応えきれていない歪みの象徴」と指摘し、体質の転換を求める労連声明を出しました。ここで徹底的に見直さないと、信頼を取り戻せなくなると考えたからです。同年7月には、現場の記者や研究者の有志で「ジャーナリズム信頼回復のための提言」をまとめ、新聞協会や各報道機関に送りました。当局取材に多くの記者を貼り付けている状況を見直し、市民社会に軸足をおいて、独自の調査報道などにリソースを集中し、双方向性が重視されるデジタル時代にあった職業文化に改めていくことを目指したものでした。
労連が積極的是正策を進めるなか、朝日新聞が業界の先陣を切って、2020年4月に「ジェンダー平等宣言」を打ち出したことは心強い動きでした。女性社員の有志が粘り強く働きかけた成果です。メディアが変わることによって、社会のよりよい変化も生み出していくプロジェクトとして、期待していました。
ただ、無理解やバックラッシュが重なり、この1年で管理職の女性割合が14.2%から 13.5%へと低下したのは残念でなりません。再成長アドバイザーの高田朝子さんが「今のままでは『ウチの会社は口だけ』という不名誉なイメージを社員に与え続けることになる」と警告していますが、女性管理職を対象にしたアンケートには「女性たちはそれぞれの部署でぶつかりながら、自分の違和感を口にすることを自分の責務として貫いている人が多いが、疲れ切って退職を選ぶ人も多い」などと悲壮感に満ちた声がつづられていました。そして、将来を担う学生たちも看板の内実を見抜きつつあります。
◇ ◇
体質改善がなかなか進まないなか、先日、創業150周年に向けて中村社長から「パーパス・ビジョン」が示されましたが、これもどこに読売などの他のメディアとの違いがあるのかが見えにくいものでした。
私たちが何のために存在するのか。「朝日らしさ」を明確にし、社会との対話を重ね、選んでもらうことは必要なことです。この数年間、私が意識してきたのは、故・筑紫哲也さんがTBS系の『NEWS23』に最後に出演したときに語った言葉です。
「力の強いもの、大きな権力に対する監視の役を果たそうとすること」
「とかく一つの方向に流れやすいこの国で、少数派であることを恐れないこと」
「多様な意見や立場を登場させることで、この社会に自由の気風を保つこと」この言葉はキャスターになる前に筑紫さんが所属した朝日新聞にも存在したDNAであり、読売とはひと味違う「朝日らしさ」につながるものでしょう。とくに大切なのが「自由」で、自由な気風で育まれた独立心のあるジャーナリストにあこがれて朝日に入社した人も少なくないと思います。
しかし、近年の経営陣のもと、そうした朝日らしさを押し潰す管理が強化されてしまいました。その象徴が、現在、問題になっている社外活動規制です。
講演料・出演料の報奨金をゼロにして、全額会社のものにするという提案は論外ですが、出版などのすべての表現活動について、編集局長室の事前検閲を事実上義務づけるルール変更にも踏み切りました。憲法が保障する表現の自由や思想信条の自由を踏みにじるもので、極めて問題が大きい内容です。現経営陣がしていることは、NHKの連続テレビ小説『らんまん』で、田邊教授が主人公に「私のものになりなさい」と迫った姿とそっくりです。
今後、朝日の社員が出す作品は激減するでしょう。なにより、自らの足元で権力者の顔色をうかがい、自由を簡単に手放す集団は、市民が自由を奪われていくことへの感度も鈍り、決して社会の自由な気風を守っていく砦になることはできません。すでに複数のメディアで問題視されているのは、これが特定個人の問題ではなく、朝日新聞が今後もリベラルなメディアとして名実ともに存在できるのかどうかの岐路に立っているとみているからです。歴代のパブリックエディターたちも「朝日は個の強い社員の多い面白い会社だと思っていたが、どんどんそうなくなっていった」と案じています。
◇ ◇
新聞労連から朝日の職場に復帰してからの3年あまりは、朝日の変質に危機感を募らせる社内外からの相談を受け、連日、大量の泥水を飲むような感覚でした。それでも、「元労連委員長」という肩書を持った人間が防波堤になり、救われる人がいるのであれば意味があるだろうと思ってきました。しかし、そうした思いが打ち砕かれたのが、昨年7月8日の安倍晋三元首相銃撃事件の深夜の出来事です。
参院選報道を仕切っていた先輩デスク(現・経営企画室)が突然、ニタニタしながら近づいてきて、「うれしそうだね」と話しかけてきたのです。人の命を暴力的に奪う殺人と、言論による安倍政権批判との区別もつかない人物が、報道の中核を担っている状況に慄然としました。「あなたのような人間はデスクの資格がないから、辞めるべきだ」と指摘しましたが、「僕、辞めろって言われちゃったよ」と茶化され、その後もしつこくつきまとわれました。
「権力に批判的な記事を書いている記者にそういう言葉を投げかけるのは、個人の問題というより、そういう風潮があるということで大きな問題だ」
後から知った同僚たちは問題視してくれましたが、冷笑に満ち溢れた管理職が跋扈する姿は、近年の幹部のもとで進んだ人心の荒廃を象徴するものだと感じています。
このデスクの言動に関する情報が一人歩きしたときの影響を考え、1年近く自分の心の内に閉じ込めていましたが、「このような組織を次世代のジャーナリストに勧めることはできない」と考えるようになりました。権力者からいくら罵声を浴びせられても動じないだけの力は身につけてきたつもりですが、身内からの冷笑は心身に堪えたのだと思います。
◇ ◇
2014年に一連の問題が起きたときに、池上コラム不掲載をめぐる経営陣の判断ミスをめぐり、200人近い社員有志の署名を集めて説明を申し入れたことがあります。「異論がある場合には意見を表明することが言論機関には不可欠だ。この申し入れは、阪神支局襲撃事件の後、『明日も喋ろう』と誓った社の姿勢に沿うものと信じています」という内容でした。あのときは苦しいバッシングのなかでも、言論や自由を大切にする朝日新聞の力を信じていたとおもいます。
しかし、「再生」を担うはずだった経営陣のもと、極めて内向きで、危機管理ばかりを強調し、朝日らしさを否定するような勢力が幅をきかせる組織になってしまいました。そして、日刊新聞法に守られるなかで、こうした経営陣を変えるすべもありません。
そう、今の朝日新聞という組織には、絶望感ではなく、絶望しかないのです。
できれば一緒に仕事を続けたかった、愛すべきメンバーと引き裂かれた悲しみは決して忘れることがないでしょう。
ただ、この「絶望」ときちんと向き合えば、朝日新聞の本来あるべき姿を取り戻せるかもしれません。
今回の退職は、あと半年待って、「選択定年」などの有利な条件で会社を離れる選択肢もありましたが、それでは本気度が伝わらないと思いました。これは、はかないけれど、朝日新聞が生まれ変わることを願った投資です。
どうか保身ではなく、次世代のために朝日新聞の人材、資産をどう生かすかを考え、殻を破って欲しい。そして、心ある人たちとは、いつかまた、日本のジャーナリズムを共に支える仲間として、一緒に働けることを願っています。
2023年10月31日
元・新聞労連委員長
南 彰


