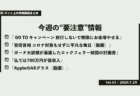沖縄戦の被害について国の責任を求めた裁判で、2018年、最高裁判所は、国の責任は認めなかったものの、沖縄戦の被害については原告の訴えを認める判決を出した。つまり司法が沖縄戦の悲惨な実態を認めたということだ。では、裁判所が認めた沖縄戦の実態とはどういうものだったのか。この裁判をフォローしてきたジャーナリストがシリーズで伝える5回目。( 文箭祥人 )
米軍の猛攻にさらされた摩文仁
「砲弾や爆風などで1日10人ぐらいの人が亡くなった」
75年前、11歳だった山城照子さんの記憶だ。
山城さんは沖縄戦が始まる前から、摩文仁に住んでいた。旧島尻郡摩文仁村波平。現在の糸満市南波平だ。母カメ(当時31歳)、妹ツギ子(同7歳)、弟憲正(同5歳)と暮らしていた。父善次郎(同32歳)は本土防衛のための兵隊としてとられ、沖縄にいなかった。善次郎は同姓同名の別人と勘違いされての招集だったということで、実際には兵隊にはならなかったということだが、何れにせよ山城さん一家は母のカメが女手一つで守るという状況だった。
1945年5月22日、米軍の猛攻にさらされた日本軍は、首里で「玉砕」するのではなく、県南部への撤退を決めた。本土決戦準備の時間稼ぎを行うためだった。日本兵約3万人と10万人と推定される住民が摩文仁を含む県南部に移動した。住民を巻き込んだ沖縄戦最後の激戦となる。山城さんはその生き証人となる。
米軍が沖縄に上陸するのは4月。この頃から、山城さん一家は部落内に親戚も避難できる大きな壕で生活をしていた。部落の家々には、県内から県南部に逃れてきた避難生活をしている人もいた。そこに米軍が砲弾を浴びせ始めた。冒頭の山城さんの言葉は、当時の惨状を振り返ったものだ。
遺体はそのままにしておくとすぐに腐敗した。山城さんは遠い親戚にあたる同級生の男の子と2人で、遺体を部落近くの山の中に運んだ。部落には、男性は兵隊にとられておらず、赤ちゃんを抱えた女性が多く残り、山城さんと同級生は貴重な働き手だった。弾が飛び交う危険な中、遺体を朝から晩までかかって山に運んだ。穴を掘ることもできず、そのまま並べて置くしかなかった。遺体に向かって手を合わせた。
「こんなところですみません。休んでください」
ある夜、山に遺体を運んだ時、水たまりを見つけ、その水を飲んだ。家族にも飲ませようと持って帰った。灯りの下でその水を見てびっくりしたという。
「真っ赤な水だったんです」
山の中では暗くて気付かなかったが、戦死者の血が混じっていたのだ。
日本軍が南部撤退をすすめていた5月末ごろ、山城さん一家と親戚が避難している壕に日本兵が4人やってきた。「鈴木軍曹」と名乗り、部下3人を引き連れて来た。
「この壕は私たちが使うから出て行くように」
鈴木軍曹は壕に入ると強い口調で命令した。この連載で頻繁に登場する日本軍の命令だ。日本軍は住民を追い出すことを当然のこととしていた。しかし、外は砲弾の嵐だ。母のカメは必死に訴えた。
「壕を出たら生きていけない。半分ずつ使いましょう」
カメの切実な願いに、鈴木軍曹はしぶしぶ承知した。日本兵4人は当然の様に、壕の奥の安全な場所を占拠した。山城さん一家らは壕の入口近くの危険な場所で暮らさざるを得なかった。
食料を取りに行かせる日本兵
山城さんと同級生の男の子は、砲撃が弱くなった夜、キャベツなどの野菜を採りに畑に行っていた。日本兵が来てからは、避難している住民より先に日本兵に食料を取られてしまうようになった。鈴木軍曹が命じた。
「食料をもっととってくるように」
6月のある日、鈴木軍曹は命じた。
「壕にいる避難者のためにニンジンなどの食料をとって来い」
その時、山城さんは曽祖父母と親戚のおじいさんとその妻と5人で外に出た。そこに米軍の砲撃が襲った。爆風であらゆるものが飛ばされた。
気が付くと曽祖父母と親戚のおじいさんは遺体となっていた。即死だった。山城さんは親戚のおじいさんに言われるままに布団をかぶっていたが、頭の左側と両足に大けがをした。血が止まらない。
「死ぬかもしれない」
山城さんはそう思ったことを覚えている。壕に連れて行かれ、塩と豚の脂を混ぜたものを傷口に当てる応急処置を受けた。頭の大きな傷を見たカメは「娘はもう生きられないだろう」と思った。
数日後、米兵が壕に手榴弾を投げ入れた。手榴弾は山城さん家族の奥へ転がっていった。そして日本兵がいた壕の奥で爆発。日本兵3人は壕の中で死亡。傷を負った鈴木軍曹はフラフラになって山城さんらの前を通って壕から出た。そして「天皇陛下万歳」と叫んでこと切れた。
安全な筈の壕の奥にいた日本兵が死に、山城さんらは助かった。カメは壕の外は危険だと判断して、5日くらい壕の中にいた。
「日本兵の遺体は腐っていき、その臭いはひどいものだった」
しかしそれは山城さんも同じだった。がけがをした頭と足はウジがわいていたことを覚えている。
そうした状態が続いて迎えた6月23日。この日、沖縄での日本兵による組織的な戦闘が終わる。米兵に「壕から出てきなさい」と声をかけられた時、もう怖がる気も起きなかった。投降してそのまま捕虜となった。
その後、県内あちこちの収容所を転々とさせられた。実家がある摩文仁村南波平に戻ったのは、沖縄戦が終わって4、5年後のことだった。
戦後も続く被害
山城さんには、二度と思い出したくない戦場の光景がある。山に遺体を運んでいたある日、砲弾を受けて亡くなった母親のお乳を飲もうとすがりつく赤ちゃん。赤ちゃんは与えられた水を口にせず、腐敗している母親のおっぱいを吸い続けた。思い出してしまうと、今でも精神的に不安定になることがあるという。
沖縄戦で受けた負傷の跡は戦後も残った。前頭部に1か所、両足合わせて6か所の傷だ。杖なしで歩くことは難しい。階段の上り下りは手すりを使っても困難だ。若い頃は頭を少し動かしただけでも頭痛がひどく、高校を卒業してから始めた仕事も集中することができなかったという。40代になると、痛みから仕事もできず、ほとんど寝たきりのような生活となった。
戦後70年にあたる2015年、精神科医の診察を受けた。山城さんは40代から50代の20年間寝たきり状態だったが、これは沖縄戦によるフラッシュバックやパニック障害などが出現し、そのことの一環として頭痛も出現したと思われると診断された。蟻塚亮二医師は、山城さんの頭痛について「沖縄戦で受けた激しい心理的な痛みによって引き起こされたと見られる」と話している。
「障害年金は難しい」と県援護課
2010年、山城さんは援護法に基づく障害年金の申請手続きをするため、沖縄県に相談した。援護法では、日本軍に食料を提供した住民を「戦闘参加者」として援護法の対象としている。実際には山城さんのように、日本軍に食料を提供したのではなく、食料を奪われたり、日本軍に危険な屋外で食料を採るよう命令されたのだが、何れにせよ、提供したと認定されれば援護法の対象となる。
ところが県の福祉援護課の担当者は消極的だった。
「認定は難しいです」
日本軍に協力したかどうかの認定がなかなか難しいという。また、山城さんの病状も加齢によるものか、沖縄戦によるものかの認定も難しいという。
結局、援護法とは何なのか?山城さんはその思いを強くして認定申請を断念した。残る道がこの沖縄戦による住民の被害を訴える裁判だった。
山城さんは陳情書で訴えている。
「私は国から謝罪も何らの補償も受けていません。謝罪の証として償ってほしい。そうすると私は身も心も楽になると思います」